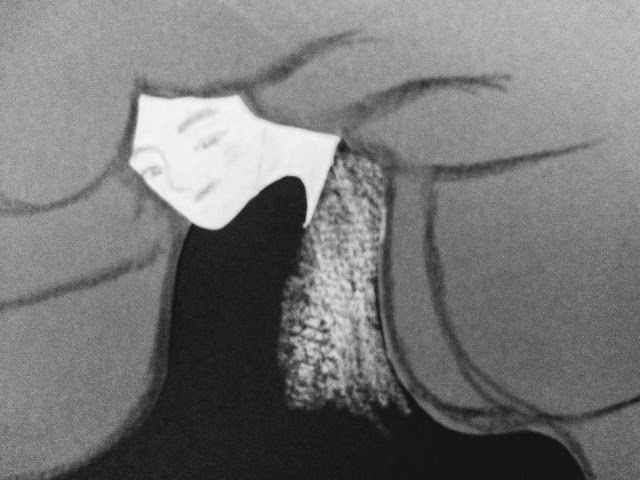この回が、「夜の訪問者」シリーズの最終回です。
<過去の「夜の訪問者」投稿>
原作戯曲が手元に残っていなかったので、確認できなかったのです。
実は「バーリング」が「バーニング」に聞こえていたのですが、ドラマを見直すと、バーリング家の工場の看板に「バーリング」と書いてありました。
あっちゃ~と思いながら、この最終回だけしっかり、「バーリング」と書きます。
さてさて
最終回を書き始めましょう。
5.苦悶と炎で
つまるところ、エヴァを死に追いやった最後の「加害者」が、バーリング家の放蕩息子、エリックだった、というオチ。
エヴァのお腹の子どもの父親だったのだ。ちなみに、エヴァはエリック対して「サラ」と名乗った。二人の関係の始まりは決して喜ぶべきいきさつではなかった。苦難に暮れるエヴァを酒場で見つけたエリックは、酔った勢いで彼女に関係を無理強いしたのだ。しかしエリックは、その後本気で彼女を愛し、妊娠を知ると彼女と結婚しようとした。ただ、御曹司とはいえ、放蕩の限りを尽くした故、父親からは信頼されるわけもなく、愛する女性を守るため、彼は父親の会社の金を横領した。
つまり、慈善団体でのエヴァの訴えに嘘は無かったのだ。
妊娠しながら、エリックの母親が理事を務める慈善団体へ、初め「ミセス・バーリング」と名乗って助けを求めたエヴァの心中に、共感する女性は少なくないだろう。
気づいてほしいと、かすかに願ったのだろうか?
助けを求める手を拒絶され、彼女は苦悶の自殺に至る。痛みにのたうちまわり、それでも、彼女は自らを死に追いやる手を緩めることなく、苦しみもだえながら、死んだ。
このあと、J.B プリースリーが世界に誇るあの名台詞が登場する。
「エヴァのように追い詰められた人々はこの世に大勢いる。
彼らの人生 希望 恐怖 苦しみや
幸せのチャンスは我々に懸かっている。
我々の考え方や 発言 行動次第なのだ。
利己主義に走らず。
互いに責任を持っていることを知らなくてはならない。
この教訓を人類が自ら学ばなければ、
強制的に教えられる・・・・
炎や 血や 苦悶を通して」
このバズーカ砲なみの攻撃力を発揮する名台詞を残して、グール刑事は去る。
このあと、ホラーな展開が待っているのだから、この作品の気のおけないとこだ。
結局、バーリング一家を不名誉への恐怖に突き落とした、その「グール刑事」という刑事が実存しないという事が判明し、誰かのいたずらなんだ! と半ば安堵仕掛けたところへ、本物の警察から連絡があり、改めて、エヴァ・スミスの自殺が正式に報告された。
私はこ作品の舞台上演を見たことがないが、きっと役者全員が斜め上、二階席辺りを見上げ暗転…という具合なのだろう。
神が文明の影にかくれた今、「自由」はもはやない。
私が疑問に思ったのは、「グール」という名前だ。原作戯曲本を読んだ当時から、疑問に思っていたが、当時はわからなかった。でも20年経って、テレビドラマとなったこの作品と再会するまでに、私にも色んな知恵がつき、この「グール」という名前の意味がわかった。中近東の神話などに登場する、死者の霊を喰らう鬼「アル・グール」のことに違いない。
日本で言うあたりの、「死神」だ。
あまりの苦悶の死にあたって、同情した死神が、復讐の天使となって、傲慢な特急階級の偽善者らに鉄拳を下しに来たのだ。
余談だが、BBCのこのドラマにおいて、グール刑事役を務めたのは、ハリー・ポッターのシリーズでルーピン先生役を好演したデイビッド・シューリスである。彼の演技はまさに死神級のシックさだ。あの名台詞をいかにも巧みに、声を荒げることなく、ひたすら淡々と染み渡らせる演技力は、まさに英国俳優ここにあり、といった感だ。
あの名台詞は、間違いなく作者プリースリーの真意を表している。
「炎と血と苦悶のなかで・・・」というのは
この芝居の時代設定が、第一次世界大戦の直前の4月なので、
第一次世界大戦の勃発を暗示している。
このセリフのそのまた奥に潜む、憂いを表しているのは
むしろ、冒頭の暗転セリフではないかと思う
青年の声: 神を信じる?
女性の声:
ええ、しんじるわ。
だって、人間は信じられない
でも何かを信じなければ・・・
裂け目から落ちてしまう。
これは、後からわかるのだが、エリックがエヴァと交わした会話なのだ。
この切なさに、人の哀れを感じてしかたがない。
エリックと交わしたということは、この言葉を口にしたとき
エヴァは、すでに、工場を追いやられ
やっと就いた新しい職場で、不当な迫害に遭い
信じていた恋人に捨てられ、
自分をレイプした若造と、
愛してもいないのに、関係していたころだ
妊娠も、すでにしていたかもしれない。
貧困と苦悩のなかで
自分の外見を呪いながら、それでも信念だけは失うまいと、
けなげに、震える脚で人生を歩もうとしていた。
日本人は平気で「無宗教」という
そして「民主主義」の名のもと、それが本当に何なのか知りもせず
「個人の自由」とやらを振りかざす。
人は人
自分は自分
あそこの家は、あそこの家
うちは、うち
恥を知るべきだと、私は思う。
神がいないところに、
「自由」などないのだ。
神のいないところでは「自由」は「勝手」に変わる。
我々は科学の発展を得て
目に見えないものは「存在しない」と錯覚するようになった。
知らなかったことについて、理屈が通るようになり
わからなかったことが、理解できるようになり
もう、自分たちにはわからないことは、ほとんどないのだ、と
錯覚している。
それも、きっと、人間の「進化」の過程だろう。
人間は進化して、神は文明の影に隠れた。
宗教は必要なくなった。
進化は当然の摂理であり、私も宗教は必要ないと考えている。
しかしそれは
信仰までが失われていいということではないはずだ!
神が、「信じる必要がない存在」になったならば
我々人間が互いに「信じ得る存在」にならなければいけなかったのだ。
そうして、我々人類は
「裂け目」に落ちてしまうのだ。
昔、知り合いが物知り顔でこういった
「私は、神を信じない。神なんていないと思う。
神がいたら、どうしてかわいそうな人や、罪もない人が不幸になるの?」
と・・・・
そもそも、神が自分たちの都合の良いよう、
物事が動くべく計らう存在だと思うこと自体が
傲慢なのだ。
神は白いひげのおじいさんではない。
永遠の存在故に、形があるわけがない。
願いをかなえてくれる、都合の良い妖精でもない。
神とはしかし
人間の念に応えるものではないだろうか。
だからこそ、我々は「善意」を持たなくてはいけないのではないだろうか。
炎と、血と、苦悶を食い止めるのは、デモ隊でも策略でもない
我々の「善意」のみなのだ。
私たち一人ひとりが、だれかを死に近づけているかもしれないのだ
そして同時に
私たち一人ひとりが、だれかを幸せにする可能性と責任を負っているのだ。